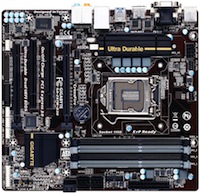Windows、OS や ハードウェアについての あれこれ。2015年1月〜2017年 →2019年〜現在 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2017/6/25 ▼2017/9/06 Window 10の更新プログラム、Creatots Updateをインストールしろと、何度もうるさくアラートを出してくるので、しょうがなくインストールしたら Amazonプライムビデオを視聴中、頻繁にシステムがクラッシュする。毎度のことだけどウンザリ。 ▼2017/9/06 最近、FirefoxとPhilips 43型ワイド液晶ディスプレイで、Amazonプライムビデオを視聴しているのだが(HD/1080p)その画質がブルーレイビデオと同等と思われる高画質なので、驚いてしまった。レンタルビデオを借りに行く機会が減ってしまった。 ■2017/6/25、AVサラウンドレシーバー DENON AVR-X1400Hを導入  以前は、2012年に購入した YAMAHA 5.1ch AVレシーバー RX-V473を使用していた。特に不満もないのだが、液晶ディスプレイをPhilips 43型ワイドBDM4350UC/11にしたので、4K / 60pに対応した、AVレシーバーにすることにした。DENON AVR-X1400Hはデフォルトのママでは、いまいちで、設定を行わないとアンプの本領を発揮しないようだ。 「HDMI端子は入力6系統(フロント1系統を含む)、出力1系統を装備。すべてのHDMI端子がデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.2」に対応しています。すべてのHDMI入出力端子が最大毎秒60フレームの4K映像信号に対応。4K / 60p入力に対応したテレビと接続することで、4K映像ならではの高精細でスムーズな映像を楽しめます。また、[ 4K / 60p / 4:4:4 / 24bit ]や[ 4K / 60p / 4:2:0 / 30bit ]、[ 4K / 60p / 4:2:2 / 36bit ]などの映像フォーマットに対応し、色情報の密度と階調性のなめらかさを両立した映像表現を可能にしました。さらに、従来のHD映像の2倍以上の広色域表現を可能にする「BT.2020」のパススルーにも対応しました。」 AVアンプの導入に伴い、何度も取っ替え引っ替え変更してきたオーディオ・ビデオ関連を整理した。  ・現在のシステム モニター:Philips 43型ワイドBDM4350UC/11 ブルーレイプレーヤー: DENON ユニバーサルブルーレイディスク プレーヤーDBT-1713UDBK AVアンプ:DENON AVR-X1400H メディアプレーヤー:ASUS O!Play Mini Plus センタースピーカー:ONKYO D-105C サイドスピーカー:B&W DM602 S3 ウーハー:DENON DSW-11R-BH/S マザボード:MSI H270 PC MATE H270、LGA1151 CPU:Celeron G3900 光学ドライブ:パイオニア BDR-208BK ドライブ:SANDISK SSDプラス SDSSDA-480G-J26C メモリー:Crucia lW4U2400CM-4G(4G×2枚) ビデオボード:XFX RX-460P2SFG5 ケース:Cooler Master製 Centurion5 電源:鎌力参-400W ケースや電源はかなり古いけどほぼ問題なし。 そのうち、PCのケースをアンプの上に乗せられる 「SilverStone SST-GD09B」などに交換してすっきりとまとめたいなと思っている。 使わなくなったのは ONKYO PCIデジタルオーディオボード SE-90PCI INTEC205シリーズHi-Fiアンプ /A-905TX ONKYOのスピカーD-102TX NEC Aterm WG300HP Windows 7pro YAMAHA RX-V473B、AVアンプ I-O DATA GV-MVP/VS USB 56K アナログモデム PL-US56K 小型スピーカーDENON SC-A11R、PCの検証用に使用 デジタルアンプKENWOOD KAF-A55は、PCの検証用に使用 ■2017/6/16 古いマザボードとCPUでWindows 7Proマシーンを再構築してみた マザボードはGA-MA785GPMT-UD2H、CPUはAMD Athlon II X4 620 /2.6GHzを使用、メモリーはDDR3-1333 2G×2枚、ケースはAntecのメヌエット(お古)を使用。 組み立てた後、Windows 7Proを新規でインストールしてみた 問題はここから、6/17から開始して、18日昼近くまでWindows Updateが続く。二度とWindows 7を新規インストールはしない。 最初、古いHDDを使用したが、音がうるさいので静かな新しいHDDに変更することにした。 それに伴い、Windows 10のSSDも 容量をアップすることにした。 電源も強化しようと思ったが、Antecの電源は特殊で、これを変更するとケースファンが搭載できなくなる。電源ファンは音がうるさい8cm薄型の2ピンのファンが使用されていた。 Windows 10のシステムは、KURO-DACHI-CLONE-U3を使用してSSDをより容量の大きな製品に丸ごとコピーし交換した。 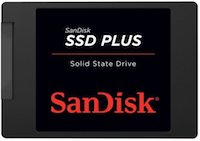 SANDISK SSDプラス SDSSDA-480G-J26C ■2017/3/29 DVDやブルーレイビデオはPowerDVD12ウルトラで視聴している。このアプリのTrueTheater エフェクト&ハードウェアデコーディングの設定で「TrueTheaterエフェクトを適用しソフトウェアデコーディングを有効にするにする」を設定すると4Kモニターで見るに絶えない画質が多少改善される。PowerDVD12ウルトラは古いソフトなので、時々ブルーレイデータを再生させると、画面になにも表示されず、音声のみになってしまう。システムを再起動すると直る。 最新のPowerDVD16ウルトラではどんな感じなのか確認のため、体験版をインストールし起動してみたら、ご覧のとうり(↓)、購入させるためのアラートが出てDVDの再生が始まらない、再生させるためには何か裏技があるのか? それとも秘密の合言葉が必要なのか? ? 即アンイストール。 ほぼ同時期に、121wareニュースの配信で届いたDMに、PowerDVD16ウルトラのセット、ダウンロード版が5,680円。となっていたので、こちらにもアクセスしてみたら、PowerDVD16ウルトラのアップグレード版であった。製品のバージョンアップグレードだと「※アップグレード対象は PowerDVD 14/15 の製品版です。」となっているが、5,680円のダウンロード版を購入して、そのまま使えるか不明なので CyberLink カスタマサポートへ問い合わせてみた。返信内容は、通常版なので、旧製品がなくてもインストールできるというので、早速購入して使ってみた。  TrueTheaterで設定しながら視聴すると、そこそこの画質で視聴できる。TrueTheaterでは、TrueTheater HD、TrueTheater Lighting、TrueTheater Color、TrueTheater Motionなどが設定できる。 Radeon Software側でも設定できるので、両方とも設定して視聴してみた。 Radeon Softwareのビデオの項目で、デフォルト、シネマクラシック、拡張、ホームビデオ、スポーツ、ヒビッド、カスタムを設定できる、視聴するソースによって設定するとそれなりの効果が期待できる。 Radeon Softwareは最新版を使用していても、かなりの確率で落ちる、そして再起動。 PowerDVD16ウルトラを購入し2ヶ月以上使用して見たが、再生できない(再生されない?)ブルーレイビデオが多数ある。最初の段階で、ディスク(データ)を読み込めない。多分DVD Fab Virtual Driveでデータをマウントしているせいなのだろう。 結局MPC-HCやVLC media playerを使用して視聴する。8500円で買えるパナソニックのブルーレイディスクプレーヤーでも、ネットワーク機能でNETFLIX(ネットフリックス)、YouTubeの再生、hulu、prime video、ネットワーク(NAS)からのコンテンツ再生(JPEG/MP4/MPEG2/MP3/WMA/WAV/ALAC/ DSD(5.6MHz/2.8MHz)/FLAC/AAC/MKV)に対応している。 PowerDVD16ウルトラでブルーレイビデオを再生しようとすると以下のようなアラートが出て、ブルーレイビデオを読み込めない。 ほとんどの場合、Windows10を再起動させると問題なく読み込める。
その後、DVD Fab Virtual Driveでマウントした仮想ディスクが再生できない場合は、最初にPowerDVD16を起動し、ブルーレイデーターフォルダ内のBDMVをドラックすれば、ディスクの読み込みができることが判明。最近はこの方法で視聴している。 あるいはDVD Fab Virtual DriveでマウントしたブルーレをPowerDVD16の左側のメニューからBDMVを選び再生ボタンをクリックして再生させている。 オーディオ用のブルーレイプレーヤーは、手軽で便利なのだが、画質を調節できない。暗く潰れてよく見えないデータはそのままだ。Power DVDや、Radeon Softwareのように色々調節できると、結局視聴するにはPCしか使わない、となってしまい、オーディオ用ブルーレイプレーヤーを買ったのは無駄だったとなってしまう。がっかり。 ■2017/2/20〜 このところ頻繁にRADEON XFX RX-460P2SFG5が落ちる、モニターの表示がグチャグチャになり、再起動してしまう。ブルーレイビデオのディスクを再生した後でも落ちる。Radeonソフトウェアは17.3.1。Windows10の問題か、多分Radeonソフトウェアの問題だろう。ONKYO PCIオーディオボード SE-90PCとINTEC205シリーズHi-Fiアンプ /A-905TXの組み合わせはやめて、KENWOOD KAF-A55 をUSBで接続した。ケーブル類をスッキリさせた。INTEC205シリーズHi-Fiアンプ /A-905TXからKENWOOD KAF-A55 を変えても私の耳では、違いはあまりわからない。 ■2017/2/7〜12 Windows 10 と Philips 43型ワイド液晶ディスプレイBDM4350UC/11の導入 Windows 7 Pro 64bitで作動しているPCは、H87チップセットとPentium G3220で作動しているのだが、ここらで古くなったWindows 7を捨て、Windows 10に移行することにした。マザボードはMSI H270 PC MATEを使い、CPUは最も低価格の第6世代Celeron G3900 、メモリーはCrucial W4U2400CM-4G(4G×2枚)ドライブはSANDISK SSDプラスシリーズの240GBを使用。 Windows 10もHomeエディションにし、チープなシステムが完成。Windows 10に移行する最大の理由は、Philips の43型ワイド液晶ディスプレイBDM4350UC/11 を使うためだ。  届いた43インチ液晶は予想よりもかなり大きかったが、以外に軽かった。Windows10を普通に起動させると、3840×2160/30hzで作動し、そのママでは文字やアンコンが小さくて認識不能。 「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」で200%で使用。Celeron G3900 では、このモニターの4K解像度の3840×2160/60hzでの表示はできないため、ビデオボードを搭載することにした。最も安い XFX RX-460P2SFG5 を搭載。これで 3840×2160/60hzでの表示が可能になった。DisplayPort 1.2を使って接続した。 その後、AVアンプと接続するため、入力はHDMIに変更した。DissplayPortが付いたAVアンプなどないわけだから、今後もHDMIが主流だろうか。
問題はここからだった。Windows 7 で使っていたアプリはみんな古いバージョンばかりでWindows10で使えるかが問題。43インチ液晶を買ったのはDVDやブルーレイビデオを大画面で見るのが大きな目的。それと4Kディスプレイの体験。動画プレイヤーは、PowerDVD12ウルトラ、VLC media player、Windows Media Player、MPC-HCを使っていた。順繰りインストールしていくつもりだったが、 最初の製品版のPowerDVD12のインストールでつまづく。ダウンロード版で購入したexeの圧縮ファイルを展開できない。なんてこった。 試行錯誤しているうちに、exeの圧縮ファイは7-zipで展開できた。 しかし、展開されたSetup.exeは相変わらず実行できない。 「・・・.exeが管理者によってブロックされています」などのアラートで終了してしまう。Intel NUCの時と同様に、Administratorアカウントをオンにするれば良さそうだが…。Windows10 proと同じと思っていたら Windows10 Homeの場合は、コマンドプロンプトでAdministratorアカウントをオンにする。 Windowsシステム・ツールからコマンドプロンプトを右クリックして管理者として実行 > このアプリがPCに変更を加えることを許可しますか? はい > net user administrator /active:yes とコマンドを入力 > コマンドは正常に終了しました で Administratorアカウントをオンする。 Administratorでログインし、Setup.exeを実行。やっとインストールできた。ここまで3時間以上かかってしまった。すでにぐったり。 Illustrator10を使っていたが、無料で使えるとされているCS2をダウンロードして、インストールしてみた。特に問題なく作動するが、Illustrator10で作ったファイルのレイアウトが崩れている。全てのファイルで修正が必要になる、ちょー面倒。ということで、アンイストール、使わないことにした。どうせIllustrator10を使うのは月に一度か二度。古いPCに、Windows7の環境を残し必要な時だけ起動することにした。そのうちWindows10でIllustrator10が作動するか試してみるつもり。 その後、Windows10でIllustrator10が作動することが判明したので、Windows7はついにお払い箱、パーツの作動テストの時だけ使用することになった。 地上デジタルTVキャプチャボード、I-O DATA GV-MVP/VSはドライバーの更新が終了したので廃棄。 USB 56K アナログモデム PL-US56Kは、ドライバーが更新されているので、搭載可能だか、もうファクスは使わないだろうから廃棄。 続いて iTunes をインストールした。インストールしてApple IDでコンピュータの認証をすると、macOS Sierra で作動しているiMacに認証コードが送られてくる。これを Windows10 に入力し認証。続いて macOS Sierra で完了ボタンをクリックする。iMac には、福島県いわき市付近で使われているコンピュータの……と、まるで違う場所を示していた。多分 Windows10 で位置情報を送るを「ON」にしていなかったからだろうか。さらに iCloud のインストールを求められ、インストールすると今度は、iPhone SE にこのコンピュータを信頼しますかとメッセージが送られてきて、確認ボタンをクリックすると Windows 10 の iCloud が認証される。 うむー、なぜ、iMacとiPhoneに別れて認証確認を求めてくるのだろう? 意味不明。 さらに、Windows 7で使っていた iTunes の認証を解除していなかったため、バラバラのパーツを再度組み立て、 iTunes の認証を解除をすることになった。こんなことをしているうちに一日が過ぎていった。 BDM4350UC/11はただの液晶モニターなので、4KテレビのようなフルHD映像を4K映像にアップコンバートする機能などはなく、DVD映像は、再生するデータにもよるが、ノイズがあったり、ぼけぼけだったりする。 MultiView 機能を搭載しているので、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。とされている。つまり搭載されている DisplayPort ×2、HDMI×2に4台のPCを接続すれば、1台のモニターを4分割して四つのシステムを表示できるわけだ。いかにみ便利そうな昨日なのだが、多分使わないと思う。 Windows 7で使っていたのはGIGABYTE H87 D3HにPentium G3220だったのだか、試しにGA-MA78GM-S2HにAthlon X4 605eを搭載し、H87で使っていたHDDをそのまま取り付けてみたら、難なくWindows 7が起動、ついでだからH87用のドライバーをアンインストールし、AMD780Gチップセット用のドライバーをインストールした。 ONKYO PCIオーディオボード SE-90PC、NTEC205シリーズHi-Fiアンプ /A-905TX、ONKYOスピカーD-102TXのアナログ時代のオーディオ環境はそのまま使用、SE-90PCはドライバーなど組み込まなくても、音が出るのでWindows10未対応ドライバーはインストールしないことにした。 (そのうちデジタルアンプ KENWOOD KAF-A55 をUSBで接続し、ONKYOのスピカーD-102TXからの出力に変更しケーブル類をスッキリさせたいと思っている。) ■2017/2/10 最近サーバーから異音がするようになってきた、かなりうるさく、気に触る。新しく導入した東芝の4T HDDの音か、古くなってきたファンのビビる音だと思っていた。 中を開けて調べたら、2016年4月にサーバーに搭載した SilverStone SST-ST75F-Pが共振し、ケースがビビっていたのだった。薄いゴムのシートをケースと当たる部分に貼ったり、電源の底に薄く切ったウレタンを挟んだりして対策。やっと静かになった。 2016年の調査では、電源の売り上げ順は Seasonic →SilverStone →Corsair →ENERMAX →Antec →Cooler Master ■2017/1/25 新しいZ270 / H270チップセットマザーボードを試してみた。MSI H270 PC MATEでテストしてみたのだか、NVMe SSD / PLEXTOR PX-512M8PeGを搭載したところ、biosで認識しない、代理店に問い合わせたところ、ベーターbiosが提供された。一応これで認識できるようになったのだか、新しいZ270 / H270チップセットの売りの一つは、M.2スロットルが二基搭載され、RAIDが組めると言うものだか、新品を購入したらとりあえずbiosアップデートってなんなんだろう。 ASUS PRIME Z270-AとNVMe SSD / PLEXTOR PX-512M8PeGでシステムを組む機会が訪れた。NVMe SSDで問題なくWindows10をインストール起動できたのだか、接続しているBlu-rayドライブからマザボードのドライバーをインストール中、LANドライバーがインストール不能。LANドライバーのアップデートを別のPCでダウンロードし、USBメモリーにコピーしインストールを試みたが、この製品にはIntel I219Vチップが搭載されていないとアラートでるだけ。Windws10がSATAを認識していないのだ。ASUSのアップデートでSATAの項目、IRST_Win7-81-10_V15201020をインストールしたら、やっと治った。 どちらの製品も、別のPCを所有していないとアウトだ。新しい製品でPCを組もうとしても、Netに接続できないとアップデートを入手できない。自作ユーザーは、ここで途方に暮れてしまう。 ■2017/1/5 Windows 7 Pro 64bitで作動しているPCに接続しているオーディオ機器を変更してみた。2001年に購入し、その後お蔵入りし、あまり使うことがなくなった、ONKYOのINTEC 205シリーズと、同時に購入したスピカーD-102TXを使ってみることにした。ONKYO PCIデジタルオーディオボード SE-90PCIと、INTEC205シリーズHi-Fiアンプ /A-905TXは、アナログのピンコードで接続し、ONKYOスピカーD-102TXから出力。スピーカーは外形寸法 幅180×高さ305×奥行272mmで低域用:13cmコーン型 高域用:2.5cmドーム型。  Windows Home Server 2011は、サポートが終了した製品なのでサーバー用0Sを探しているのだが、なかなかこれといったものがなく、NASに移行しようかと考えた。しかし、以前Windows Home Server 2011でHDDに障害が発生した時、問題のないデータの大部分を救出できたので、しばらくはWindows Home Server 2011を使うことにした。 ■2016/10/ 30 Windows 7 Pro 64bitで作動しているPCは、ONKYO PCIデジタルオーディオボード SE-90PCIを内蔵し、デジタルアンプKENWOOD KAF-A55に接続、小型スピーカーDENON SC-A11Rで音声を出力していたのだが、SE-90PCIをとりはずし、デジタルアンプKENWOOD KAF-A55とUSBで接続することにした。  ONKYO PCIデジタルオーディオボード SE-90PCIと デジタルアンプKENWOOD KAF-A55  外形寸法 105(W)×170(H)×126(D)mm ■2016/9/10 Bluetooth対応カナルイヤホン「EVEREST(エベレスト) 100」を購入。Bluetooth Ver.4.0に対応したBluetooth USBアダプタMM-BTUD44を導入し、Windows 7が稼働しているPCで使用しペアリング。 過去に使用してきたBluetooth製品から音声は格段に進化したした感じだが、やはり音切れが起る。PCの地上デジタルキャプチャボードで放送を視聴すると、かなり映像と音声がずれ、口の動きと音声が一致しないのが気になる。DVDビデオなどはあまり気にならないがそれでも音が遅れている。ファームウェアを2.6にアップデートし、多少良くなった感じだ。  iPhon SEでの音楽の視聴はとても良好。ASUS ZenPad 8.0 /Z380Cではさらに音が良く、Android用に開発されたBluetoothイヤホンなのかと思えるほどだ。ZenPadでサーバーからのWi-Fiでストリーミング再生した音楽もお途切れ無く再生できた、てっことはPC用のBluetooth USBアダプタがしょぼいのかも。 EVEREST 700、EVEREST 300、EVEREST 100のファームウェアアップデート http://support.harman-japan.co.jp/update/Everest.php ■2016/7/5 Windows 10とintel NUCの組み合わせで、サーバーからのストリーミング再生時、ブルーレイデータの音声・映像が途切れる問題はさらに酷くなり、まともに再生できなくなってきた。原因は不明だが、とりあえずWindows8に戻すことにした。丸一日かけて最初からインストールし直した。 状態は、Windows 8、有線LAN、Bluetooth接続のマウス、オーディオはToslinkアダプターを使ったOpticaでAVアンプと接続、HDMIからは映像のみをAVアンプを経由しないで直接テレビに出力。再生にはCyberLink PowerDVD12 Ultraを使用している。音声・映像とも問題なく再生できる様になった。 さらに、当初の予定通り、Bluetooth接続のマウス、HDMIから音声・映像をAVアンプ経由で液晶テレビに出力が可能になった。ただ無線LANはでは症状が改善されないため、有線LANのまま使用。 Windows 8で使用するなら、 GA-MA78GM-S2H + Athlon II X2 250e + Radeon HD 4350 のままで良かったということになる。またしても、お金と時間をただ浪費しただけとなった。良かったのは省スペースになったことぐらい……。残念。 Windows8.1にアップグレード、本来Windows8.1用のドライバー類がインテルのユーティリティソフトで自動で検索、インストールされた。インテル NUC5PPYHは元々Windows8.1で使う様に作られたとものと思われる。 ■2016/4/4 Windows 7が作動するPCの電源ファンが、かなり前から時々カタカタと異音がしていた。製品は2008年ころのENELMAX LIBERTY ELT500AWT。元々ファンに問題があり、メーカーが無料で修理対応していたモデルだが、私のは問題なく作動していた。 いつかはファンを交換しようと思っていたのだが、ほったらかしだった。そろそろと思い分解してみたら、何とファンよりもコンデンサーが膨らんで液漏れしていた。2次側で高い耐久性を求められるとされているコンデンサーだ。こんな状態でトラブル無く作動していたものだと、関心した。 8年も使ったので廃棄することにした。   実はこの電源をもう1台持っている。製品のテストのために時々しか使わないものなので、分解してみたが、きれいなものだった。これを使おうと思い組み込んだが、PCが起動しない。電源単体でのテストでは問題なく作動するが、マザボードに接続すると起動しない。原因不明 ? これもゴミか。面倒なので2台とも分解し分別して捨てた。  SST-ST75F-P 結局LIBERTY ELT500AWTは諦めて、他の製品テスト用の SilverStone STRIDER PLUS SST-ST75F-P(2012年頃の製品)をサーバーに取り付けた。サーバーに搭載していたサイズの鎌力参-400W(2006年ころの製品)をWindows 7が作動するPCに搭載することにした。  鎌力参-400W これもかなり古い製品なので、Z87チップセット+Pentium G3220で作動するか心配だが問題なく起動。 ついでにWindows Home Server 2011のシステムドライブを交換することにした。サーバーは2011年から使用でOSがインストールされているSeagate ST3500418AS / 500GB(2009年ころの製品)もこの時から使用。問題なく使えていたが、最近、ブレーカーが落ちた時にクラッシュした様で不良セクターが発生。 使用していない Western Digita の Caviar Blue WD10EALX /1T(2010年頃の製品)があったので、これにOSをインストールすることにしたが、面倒なので、玄人志向のKURO-DACHI/CLONE/U3の「パソコンなしでまるごとコピー」機能を使い500Gから1Tに全体をコピーしてみた。 ST3500418AS/500GBは、システム→C / 60GB、データ→D / 440GBで分割して使用していた。コピーした結果全く同でシステム→C / 60GB、データ→D / 440GBで残りが未使用となっていたので。パーティション拡張で、システム→C / 60GB、データ→D / 残り全部となった。(2016/4/6)  KURO-DACHI/CLONE/U3 サーバーのケースは2012年10月から Fractal Design Define miniを使用している。MicroATXサイズでハードディスクが6台搭載できる。 特徴の一つ、ケーブルマネージメント設計とは、ケーブル類をケースの右サイドの裏側に回し、ケース内部をすっきりとさせ、効果的なエアフローを確保できるとされるもの。そのケーブルを裏側に回す穴のゴムのガイドが劣化してしまい、黒い粉と化し、触ると手が真っ黒。全部取り外し棄てた。   
■2016/1/18、NUCを導入(NUCとは=Next Unit of Computing) intel NUC Kit NUC5PPYH (BOXNUC5PPYH)を導入 http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/nuc/nuc-kit-nuc5ppyh.html Pentium N3700(最高2.4GHz、TDP 6W) DDR3L-1333/1600 SO-DIMM×1(最大8GB、1.35V対応) ストレージは厚さ9.5mmまでの2.5インチHDD/SSDが1基内蔵可能 M.2 2230スロットにIntel Wireless AC3165装着済 (802.11ac, BT4.0) Gigabit Ethernet /Realtek 8111HN  Windows 8.0で動いているPC(※↓)も古くなり、Wondows 10に対応するドライバも提供されなくなったため、そろそろ新しくしたいと思っていたのだけれど、DVDやブルーレイデータを再生するためにだけ使っていたので、PCでは無くブルーレイデータを再生できるネットワークメディアプレイヤーで十分なのではと悩んだ。特に価格の問題で。結局低コストで導入できるNUCを試してみることにした。  (※GIGABYT GA-MA78GM-S2H、Athlon II X2 250e、Radeon HD 4350 ) バリュータイプ小型ベアボーンキットで、第8世代のintel HD Graphicsを搭載 HEVC(H.265)デコードと4K解像度出力が可能されている。CPUはintel Pentium N3700/2.4Ghz、4コア/4スレッド / TDP6Wをオンボード上に搭載、DDR3L SODIMMを1枚と、2.5インチHDDか2.5インチSSDを1台搭載可能。 手のひらサイズのPCで、サイズは11.5×11.1×5.1cmと弁当箱程度の大きさ。 メモリーは、A-DATA ADDS1600W8G11-R_8GB、SSDはCrucialのCT240BX200SSD1_240GBを内蔵しシステムの設定を行った。 OSは、古い機種で使用していたWindows 8Pro 64bit をDVDディスクからインストール(USBで接続できる外付けDVDドライブが必要)。その後、Windowsアップデートが始まり、時間ばかりが過ぎて行き、寝てしまた。本体の設定と、Windowsアップデートでまる1日費やした。 172項目アップデートされる。笑うしかないな、OSのクリーンインストーなどありえない。(二度とやらないと心に誓う。) (最初に、F-10でブートデバイスの選択から、USBで接続されたDVDドライブを選択しインストールを開始する。終了後に起動しない場合は、再びF-10からOSをインストールしたデバイスを選び再起動) ここでいきなりWindows10へのアップグレードを実行してみた(Win8.1アップデートはスルー)。なんと成功、以外に簡単にアップグレード出来、認証も問題ない。それから、インテルのドライバーをインストール。そして肝心のPowerDVD12をインストールしようとしたが「このアプリは保護のためブロックされました」でインストールできなかった。 ネット調べたら、Administratorアカウントを有効にして、Administratorでログインし、インストールするとなっていた。それで成功。次は無線LANの設定、なかなか接続できなかったが、接続完了。今日も24時までかかった。これで一応、予定どうり、DVDやブルーレイデータの再生専用マシーン完成。 (コンピュータの管理→ローカルユーザーとグループからユーザー→Administratorのプロパティ) コントロールパネル → 管理ツール → ローカルセキュリティー・ポリシーを開く セキュリティの設定の中にある ローカルポリシー → セキュリティーオプションを開く 右側みると、「アカウント:Administratorアカウントの状態」 というのがあるので これを開きAdministratorを有効に ▼Windows 10とintel NUC NUC5PPYH。Bluetoothマウスの問題。 時々マウスが動かなくなる。 つまりBluetooth マウスの接続が切れる 「電源の管理」タブを選択し、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外すことで解決。 ▼Windows 10とintel NUC NUC5PPYH。サーバーからのストリーミング再生時、ブルーレイデータの音声・映像が途切れる問題。 本体は、無線LAN、Bluetooth接続のマウスを使用、キーボードは無しで、必要な時はスクリーンキーボードを使用、HDMIから音声・映像をAVアンプ経由で液晶テレビに出力。ケーブルは電源とHDMIの2本でとてもスマート。さっそくPowerDVD12でサーバー上にあるブルーレイデータを再生してみた。音声・映像が途切れて視聴不能。 とりあえずドライバーのアップデートを試すが、変化無し。無線LANを止めて有線にしてみたが変化無し。試行錯誤した結果、HDMIからの音声・映像出力に問題があるという結論に達した。 HDMIケーブル一本で音声・映像をAVアンプに出力で、全てが間に合うと思っていたのに、従来どうりの状態に戻ってしまった。結局、無線から有線LANに、Bluetooth接続のマウスはそのまま、オーディオはToslinkアダプターを使ったOpticaでAVアンプと接続、HDMIからは映像のみをAVアンプを経由しないで直接テレビに出力。 なんだかなー。インテルのドライバーの問題か?? このタイプPCの限界か ??
■2015/4/25、Windows 8 Windows 8.0で動いているPCは、32インチの液晶テレビをモニターとして、DVDやブルーレイデータを再生するために使っている。ブルーレビデオを見ていた時、HDDが激しく作動しWindows Up date が何かをダウロードしビデオを見ている最中に「Windows8.1にアップデートすると」警告がでた。キャンセルして、映画を見ていたが、「後○分後に再起動」とまた、警告、キャンセルしたが、ついに勝手に再起動しWindows8.1をインストールし始めた。 それは、Windows Updateの設定が 「更新プログラムを自動的にインストール」の設定になっていたのだった。 ここは、「更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかは選択する」が正解だろう。なんてこった。 このPCは、古いハードウェアを使用しているため、ビデオボード(Radeon HD 4350)のドライバーがWindows 8.0対応までしかない。そのためWindows8.1にアップグレードするとPowerDVD12でブルーレビデオを再生できない、などの理由でWindows 8.0を使っていたが、またしても面倒な事になってしまった。 再起動したWindows8.1では案の定PowerDVD12でブルーレビデオが再生できなくなっていた。それから延々4時間かかって(Windows Updateだけでも135個もある)PCを元の状態に戻したが、テレビ台の中にキレイに収納してあったのを取り出してセットアップしたため、また明日、整理をしなければいけない。 今日もひたすら忍耐。ぶちきれて何かを壊してしまいそう。 ・OSのアップデートが実行されるとは思っていなかった Windows Up dateが勝手にOSのアップデートを行うとは思ってもいなかったので、自動のままにしていたのが大失敗だ。PCを使うために、またしても時間を浪費してしまった。ほんとにうんざりだ。 Windowsには「ユーザーの許可無く一切ダウンロード・インスール・変更は出来ない」ボタンが何よりも重要な気がする。 ■2015/3/4 無線LANルーター 無線LANルーター、NEC Aterm WG300HPをフレッツ光のポイントで購入 室内のネットワークを見直した。NTTのONU、ハブが2台、無線LANルーターが1台あったのを、ハブを1台撤去できたので少しすっきりした感じだ。 NTT-ONU・RV-S340NE→ |→NEC Aterm WG300HP、無線LANルーター |→corega CO-BSW08GTX、8ポートハブ |→DENON DBT-1713UDBK、ブルーレイプレイヤー →YAMAHA RX-V473B |→ASUS O!Play、ネットワークメディアプレイヤー →YAMAHA RX-V473B |→YAMAHA RX-V473B、AVアンプ → 32インチ東芝テレビ |→ Windows 8 Pro → 32インチ東芝テレビ |→ Windows Home Server |→ Windows 7pro → SE-90PCI →KENWOOD KAF-A55 |→ iMac OSX10.7.5 → レザープリンター ■普段は、Mac OSX Lion10.7.5とPCはWindows 7 Pro 64bitを使っているのだが、Windowsの日本語入力・変換に使われているMicrosoft IMEの変換効率が悪く(と言うよりカス。今はGoogle日本語入力を使っている)、HTMLの編集、製作などほとんどiMacを使っている。Windows 7が作動するPCはAVマシーン化し、iTunesの再生、DVDビデオの再生、Blu-rayビデオの再生。地デジの視聴、動画の編集・変換などに使っている。そもそもWindowsがビシネスマシーンで、Macが趣味とかって考えはおかしくて、Windowsこそが趣味で使う機械で、たいして拡張もできないMacこそがビジネスマシーンなのではないかと思う。 音声は、ONKYO PCIデジタルオーディオボード SE-90PCIをPCに内蔵し、デジタルアンプKENWOOD KAF-A55に接続、小型スピーカーDENON SC-A11Rで出力   外形寸法 105(W)×170(H)×126(D)mm |
・2017/2/7から2018/8/19 ■PHILIPS BDM4350UC/11 IPS LCD、42.51 インチ(108 cm) 3840 x 2160(60Hz の場合) 応答時間(標準値) 5 ミリ秒(GTG) 明るさ 300 カンデラ コントラスト比(標準値) 1200:1 ピクセルピッチ 0.2451 x 0.2451mm 表示角度 178度(横)/178度(縦) 通常動作時 63.1 W(typ.) (EnergyStar 6.0 テスト方式)  ▼今まで使用していた LG 23MP65VQ-Pは、 2017/2/7、サブモニターに 縁なしでかっこいいのだけど、真ん中のLGのロゴがあるあたり、パネルと筐体の間に隙間が出来ている。両面テープみたいな白いものが隙間から見えてかっこわるい。 電源ボタンなとがタッチセンサー式ですぐ隣のiMacのスイッチを入れただけでONになってしまう。また軽く触れただけでOFFになってしまので、地デジチュナーが作動していると、モニターがOFFになった瞬間アプリケーションが異常終了してしまう。電顕ボタン類は普通にスイッチで良いのでは。  ▼壊れた LG W2042TQ-BF ▼2014/7/1 2008/5/15からPCで使用している液晶モニター死亡。 症状は、スイッチを入れ、Windowsが起動、メーカーロゴ画面やWindowsロゴ画面までは表示されるが、ディスクトップが表示されたとたんに画面が消えるというもの。ネットで調べたら典型的な液晶モニターの故障パターンのようだ。しょうがなく新しいモニターを購入。また、LGを買ってしまった。 ▼2015/3/24 そのまま放置していた壊れたLG W2042TQ-BFをやっとパソコンファームへ発送し、廃棄した。 ■2011年 iMacを購入とともにWindows Home Server 2011を導入した。またOSX LionのTime Machine用にUSB接続の250GBのハードディスクを取り付けた。 Power Mac G5が壊れた時、ちゃんとバックアップしたつもりだったが、大量のファイルを失った。やっぱりデータはサーバーで管理すべきだ。Mac本体が壊れた時は被害も出費も大きいが、PCの場合、HDDさえ壊れなければ、パーツ単位でハードウェアを交換できるので、安く修復できるのがいい。 ▼iTunesはMacからWindowsに ・iTunesは既にMacからWindows 7が作動するPCに移行している。Power Mac G5を使っていた時にMac OSX10.4xで作動するiTunesのサポートが終了したので、Windows 7が作動するPCに移行した。Power Mac G5が壊れ、後続のiMacに移行。iTunesをWindowsからMacに戻すのは面倒なので、このままWindows で使うことにした。 MacよりもPCの方が音がいいはずだ。 PCの場合、ハードウェアの選択肢が豊富で、好みのPCを作ることが可能だ。現在PCには ONKYO PCIデジタルオーディオボード SE-90PCI を搭載している。 Windows Home Server 2011に保存したデータをiMacとPCのiTunesでうまく共有出来ないことが判明。「 iTunes Library.itlは、ライブラリ内の曲およびユーザが作成したプレイリストのデータベース曲固有のデータがこのファイルに保存されます。 iTunes Library.xml は、ミュージックやプレイリストをコンピュータ上のほかのアプリケーションでも使えるようにする」とされていますが、普段はPC上でiTunesデータを管理したり、視聴している。iMacでもiTunesを使おうとServeのiTunesフォルダにアクセスし視聴。その後、PC側でiTunesを起動すると、曲の場所が分からないと表示されます。 iTunes Library.itlが書き変わるのか? 毎回データの場所を探すのが面倒なので、iMacではiTunesを使わなくなってしまった。 ▼マウスについてあれこれ…。 Windows 7が作動するPCはLogicoolのMX 620 コードレス レーザー マウス。iMacには Logicool の M525 を接続している。 Windows 7のMX 620の反応が鈍く、電池を交換したり、レシーバーをマウスの側に置いてみたりしてみたが、右クリックの反応が相変わらず鈍いままだ。そんな状態でいらいらしなが使い続けていた。ついに、 MX 620からM525に繋ぎ変えた。反応が鈍かった右クリックが普通に使えるではないか。ということは今まで使っていたMX 620が製品として古いから反応が鈍かったという事なのだろうか。M525をWindows 7で使い、iMac用に新たにマウスを導入することにした。MX 620はお役御免。  Logicool MX 620(廃棄) ▼2015/3/26。 MX 505死亡。 Windows 8.0搭載マシーンに Logicool の MX 505を使っていが、たいして使わないうちに壊れる  Logicool MX 505(廃棄) ・2015/9/26。M525を壊す。 Windows 7で使っていたLogicool のM525が最近よくフリーズし止まってしまう。電池を出して、入れ直すともとに戻る。そんなことを繰り返しているうちに、ついにぶち切れて床に叩き付けて破壊してしまった。  M525 (廃棄) M525の後続はM546。Windows 7搭載マシーンで使用。  Logicool M546(使用中) iMac用にM557を使用。残念な事に形が悪く、意識しないで使っていとき、不用意に右のボタンを押してしまう。ボタンのクリックが軽いからかもしれない。その後M557のマウスの中央のボタンやホイルを押すと、電下が入いりペアリングを開始し動く事が判明。M525の様に指がのるところがくぼんでいれば良かったのに。  Logicool M557(廃棄) BUFFALO BSMBB26SBK ついにLogicool以外のマウスを導入。さっそくiMacに接続してみたが、カクカク動いて使えない。これもだめかと思いWindows に接続したら、とても使いやすい、PCの電源を切るとスリープし、PCを起動後マウスを動かすとスリープ解除される。  Bluetooth 3.0対応 BlueLEDマウス Bluetooth 3.0 Class2、BlueLED光学式、1000dpi、電波周波数:2.4GHz  KURO-DACHI/CLONE/U3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||