|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリに関するあれこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリーの搭載量がシステムのパフォーマンスに大きな影響を与えるのはなぜ。 現在のOSはハードディスクの一部を仮想メモリとして使用しています。メモリーの空き容量が不足したとき、メモリー内のデータをハードディスク(ページファイル)に一時退避し、必要に応じてハードディスクからメモリーにデータを戻します。メモリーが少ないとページファイルとメモリの交換作業が頻繁におこり(スワップする)、ハードディスクはデータの読み書きが遅いためCPUの処理が滞ってしまい、結果としてパフォーマンスがおちることになります。
DDR-266B : PC2100でCASレイテンシが2.5のDDR SDRAMのこと ■CAS latency(CASレイテンシ、CL3-4-3-9の場合) 格子状に並ぶ記録部分にアクセスするために行と列を指定します。行アドレスを伝える信号をRAS、列アドレスを伝える信号をCASと言います。それに費やす時間がレイテンシ。
■CASレーテンシとは何ですか?(エルピーダメモリのFAQより) CASレーテンシとはカラム(列)アドレスを与えてからデータが読み出せるようになるまでの時間がクロックいくつ分になるかを表したものです。CL=2なら2クロック後に、CL=3なら3クロック後にデータが出力されます。 ■SPDとは何ですか?(エルピーダメモリのFAQより) Serial Presence Detectの略で、SPDもしくはシリアルPDと呼ばれています。実態はシリアル(1ビットI/Oの)EEPROMであり、DRAMの種類や容量、アクセススピードなどメモリモジュールの仕様情報が格納されています。PC側で、このSPDを読み込むことにより、そのモジュールに合わせた適切なタイミングを自動的に設定することが可能となります。 ■ECCとは何ですか?(エルピーダメモリのFAQより) Error Correction Codeの略で、メモリ内のデータエラー発生の有無をチェックすると同時にエラーを補正する機能です。 具体的には、データを受け取った側で、そのデータの中に、転送途中に発生した誤りがあることを検出し、かつ、元の正しいデータに訂正できるように一定の規則に基づいた冗長ビットを含ませた送信データをいいます。 ■RegisteredモジュールとUnbufferedモジュールの違いを教えてください。 Registeredモジュールは、メモリモジュール上のレジスタを介してデータの転送を行うメモリモジュールです。 アドレス、コマンド信号をいったんレジスタに格納しPLLに同期して一斉に出力するため、モジュールに搭載する単体が増加しても、信号を安定して伝送することができます。このためRegisteredモジュールは大容量・高信頼性が必要なサーバ/ワークステーションに最適です。 これに対して、Unbufferedモジュールは上記のようなレジスタを持たない構成で、主にコンシューマ用途のPCで利用されています。(エルピーダメモリのFAQより) ■SDRAMメモリモジュールの製造コストを下げる方法として使われる4層基板 メモリモジュールは、信号線を通す基板と電源を通す基板を積み重ねて作られている。メモリモジュールは,規格化団体の「JEDECジェデック」(Joint Electron Device En gineering Council)が6層構造の基板を前提とした設計を示している。 独自に設計し直し基板を4層した製品も存在する。4層にするには配線の間隔を詰めるなどの工夫を行なうわけですが,それだけ各信号線間のノイズ干渉が増えることになります。 ■NVIDIA、オーバークロック性能を提供するメモリ新規格「EPP」を発表 EPPは、現在、メモリモジュール上に実装されている「SPD(Serial Presence Detect)」の拡張規格。SPDチップには、クロック周波数や信号タイミングなど、動作に必要な基本的な情報が格納され、EPPでは、さらにコマンドレートやメモリ電圧など、SPDでは省略されている仕様情報も規定。これにより初心者でも簡単にオーバークロックが行えるようになるとされています。EPPメモリを利用するにはに対応するBIOSが必要。NVIDIAのチップセット「nForce 590 SLI 」を搭載するマザーボードはEPPに対応。 ■XMP(Extreme Memory Profile):Intelが提唱しているメモリの拡張規格。JEDECで採用されているSPDを拡張したもので、DDR3-1600のようなJEDEC仕様が存在しないメモリでも、JEDEC標準規格のメモリと同じように自動認識できるようになっている。Intelの「エクストリーム」シリーズのマザーボードで対応するという。 ■FB-DIMM メモリモジュール上のDDR2メモリとチップセットの間に、データの受け渡しを行なう役割を持つAMB(Advanced Memory Buffer)と呼ばれるチップを搭載し、メモリに読み書きされるデータをAMBを通して順番にメモリやチップセットに渡さす仕組み。通信が1対1で行なわれるため、高クロックでの通信が行なえる。(Ascii24・Akiba2GO-06/6/19) MacProは、2枚のメモリライザカードに8つのFB-DIMMスロット(1枚のカードに4つのスロット)。最大16GBのメインメモリをサポート。 独立した4つのメモリチャネルで最大256ビット幅。大型のヒートシンクが必須。 ■デュアル・チャネル (インターリーブ) モード デュアル・チャネル・モード は、両方の DIMM チャネルにインストールされたメモリーの容量が均等な場合に有効になります。 テクノロジーとデバイスの幅は、1 つのチャネルとその他が変化させることも可能ですが、各チャネルにインストールされたメモリーの容量が均等である必要がありますのでご注意ください。 動作速度の異なる DIMM をチャネル間で使用すると、メモリーの使用速度が遅くなってしまいます。 デュアル・チャネル・モードを有効にするためのルール デュアル・チャネル・モードを構成するには、以下の条件に合致する必要があります: 各チャネルのDIMM設定が一致すること 同じ容量であること (128MB、256MB、512MB など) メモリーチャネル A と B の両方が一致すること メモリースロットを対称使用すること (Slot 0 または Slot 1) 同一ブランドである事、同じメモリータイミングであること、同じ DDR スピードであること 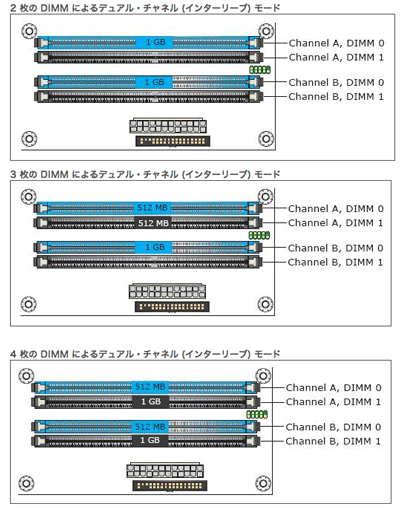
■CPUと対応するメモリー CPUのデータ転送帯域とメモリーのデータ転送帯域を同等にする必要があります。 ※データ転送帯域:1秒間に転送できるデータ量。 (例) ・Pentium4/3.06GHz/FSB533のデータ転送帯域は3.2GB/秒 DDR333(2.7GB/秒×2=データ転送帯域は5.4GB/秒)をデュアルチャンネルで作動。 ・Pentium4 3.06GHz FSB533のデータ転送帯域は3.2GB/秒 DDR400(データ転送帯域は3.2GB/秒)をシングルチャンネルで作動。 ・Pentium4 3.06GHz FSB533のデータ転送帯域は3.2GB/秒 DDR266 (2.1GB/秒×2=データ転送帯域は4.2GB/秒)をデュアルチャンネルで作動。 ・Pentium4 2.4C〜3.2 GHz FSB800のデータ転送帯域は6.4GB/秒 DDR400 (3.2GB/秒×2=データ転送帯域は6.4GB/秒)をデュアルチャンネルで作動。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
